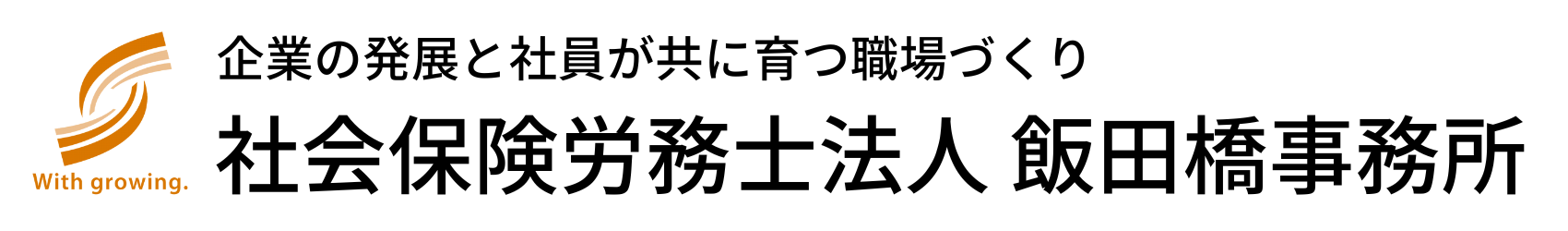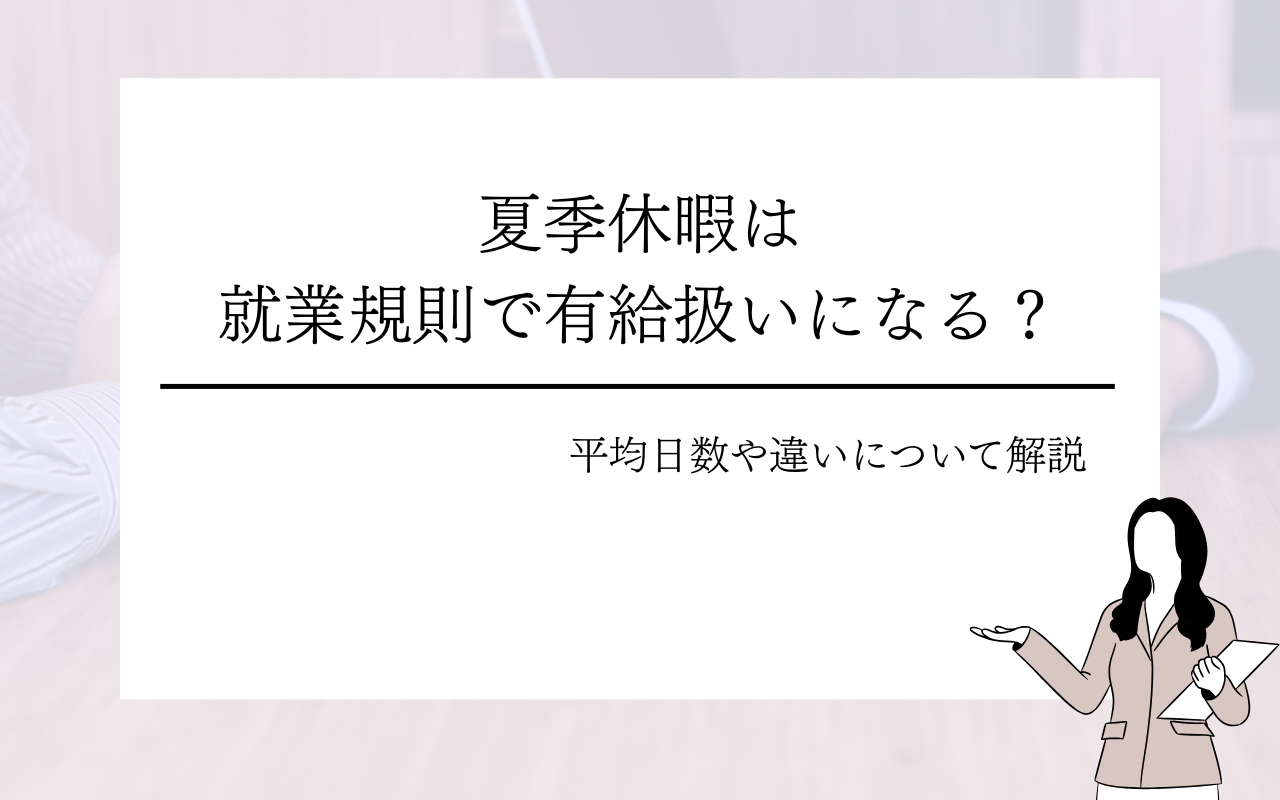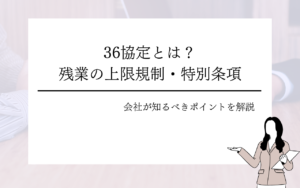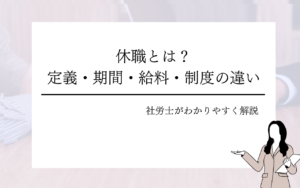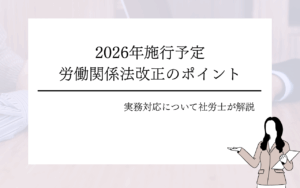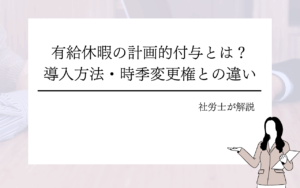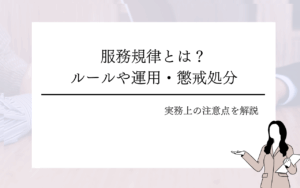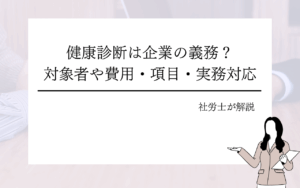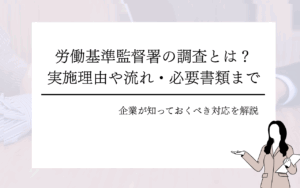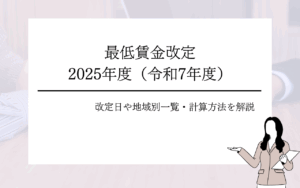夏休みやお盆休みという文化がある日本では、心身のリフレッシュや家庭の都合も踏まえて「夏季休暇」を導入する企業が増えています。
労働者としては嬉しい制度ですが、経営者や人事・労務担当者の立場になると「夏季休暇は有給扱いでよいのか?」「付与しないと違法になるのか?」といった疑問を抱くこともあるでしょう。
本記事では、夏季休暇の就業規則上の扱いや、有給休暇との違い、付与義務の有無などを解説します。
自社の制度を見直したい、夏季休暇の導入を検討している企業の担当者の方はぜひご覧ください。
夏季休暇の就業規則上の扱いとは?

夏季休暇は、就業規則上どのように扱われるのでしょうか。
普通の休日なのか、有給として扱われるのか、夏季休暇の区分や違いについて解説します。
就業規則上は有給休暇ではなく法定外休暇
結論「夏季休暇」は労働基準法で定められた法定休暇ではありません。
あくまで、企業が任意で就業規則や労使協定などに基づいて設定する「法定外休暇」に該当します。
労働基準法で企業に付与義務があるのは「年次有給休暇」や「産前産後休業」など一部の休暇に限られており、夏季休暇は対象に含まれていません。
そのため、夏季休暇の有無や付与日数、取得時期などは企業ごとに自由に決めることができます。
夏期休暇との違い
「夏季休暇」と「夏期休暇」は単なる表記上の違いであり、法的な違いはありません。
ただし、企業によっては「お盆休み(8月13日〜15日前後)」を「夏期休暇」と呼び、それ以外に自由に取得できる休暇を「夏季休暇」と区別している例もあります。
有給休暇との違い
前述のとおり、夏季休暇は年次有給休暇とは異なる制度です。
年次有給休暇は労働基準法第39条に基づき、雇入れ後6か月間継続勤務し、かつ所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、年10日以上を付与することが法的に義務付けられています。
一方、夏季休暇は付与義務がなく、仮に「有給扱い」であっても法定休暇ではありません。
そのため、就業規則や労使協定で「無給」と定めることも可能です。
夏季休暇に給料は発生するかどうかは会社次第
夏季休暇が「有給扱い」か「無給扱い」かは、就業規則などの定め方によって異なります。
多くの企業では「有給として給与を支払う」か「年次有給休暇の計画的付与を利用する」形を採用していますが、業種や規模によっては「無給」とするケースも見られます。
無給とする場合は、事前に就業規則への明記が必須です。
ただ、夏季休暇を設定する場合には、一般的には有給とすることがほぼ当然の認識となっています。
夏季休暇の平均日数と付与義務について

夏季休暇の導入は義務ではないため、企業によって制度の有無や付与日数は異なります。
一般的に、夏季休暇として設定される日数の平均は4.4日となっています。
特に、お盆の時期(8月13日〜15日)を含めて夏季休暇を設定している企業が多いです。
制度を設けていない企業では、従業員が年次有給休暇を活用して夏季に休みを取る傾向が強いため、業務が一時的に停滞するリスクがあります。
近年では、ワークライフバランスが求職者の間で重視されている面もあり、夏季休暇を導入する企業も増えてきています。
夏季休暇を導入する際には、制度設計の際に以下のポイントを押さえておきましょう。
・付与対象者の範囲(正社員のみか、契約社員・パートも含むか)
・入社直後の従業員への適用可否
・有給・無給の区分
・年度単位の繰越や分割取得の可否
労使間で十分に話し合い、労働者の納得を得られる形で導入を進めていきましょう。
夏季休暇を付与しない場合有給取得申請は却下できる?

自社で夏季休暇制度を設けていない場合に、従業員が年次有給休暇を使ってお盆期間などに休みたい」と言ってきたら断れるのでしょうか。
結論として、年次有給休暇の申請は原則として拒否できません。
労働基準法第39条第5項により、労働者は時季(取得日)を指定して有給休暇の取得を請求でき、会社側はそれを与えなければならない義務が定義されています。
正常な運営を妨げる場合は時季変更権が認められる
基本的には、有給休暇の申請を却下することはできませんが、労働基準法第39条第5項には、次のような規定があります。
「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
引用:労働基準法第39条第5項
会社には、業務上どうしても休まれると困るという正当な理由がある場合に限り、有給の取得日を変更できる権利(時季変更権)が認められています。
しかし、この権利を行使するのは簡単ではありません。
例えば、特定の繁忙期で代替要員が確保できない場合や、休暇が集中し業務が著しく停滞する恐れがある場合など、明確な理由が求められます。
単純に「忙しそうだから」「できれば出てほしい」といった主観的な理由では、時季変更権の行使は無効とされる可能性が高いでしょう。
有給休暇の計画的付与を活用しよう
業務の繁閑に合わせて有給休暇の取得を調整したい場合には、あらかじめ「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しておくこともおすすめです。
これは、年5日の時季指定義務を除いた残りの有給日数について、会社側があらかじめ取得日を割り当てることができる制度です。(労働基準法第39条第6項)
計画的付与を使用すれば、「お盆の期間に一斉休業」といった形で業務全体を調整しやすくなります。
結果として、有給休暇の消化率向上にもつながり、働き方改革への対策としても有効です。
夏季休暇制度を導入する3つのメリット

夏季休暇は法律上の義務ではないものの、福利厚生として導入することには多くのメリットがあります。
単なる休み以上の意味を持つ夏季休暇制度を3つの観点から整理します。
従業員満足度や定着率の向上につながる
最もわかりやすいメリットは、従業員の満足度やモチベーションの向上です。
特に近年は、仕事とプライベートのバランスを重視する傾向が強まっており、企業の福利厚生制度によって転職を検討する方も多いです。
夏季休暇のような制度があることで、従業員満足度の向上や離職防止につながります。
生産性向上や業務の標準化・属人化の予防になる
夏季休暇を定期的に導入しておくことで、業務の引き継ぎや担当者不在時の対応マニュアルなどが整備され、業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。
また、心身のリフレッシュにもつながり、生産性の向上も期待できるでしょう。
ワークライフバランスなど求人でのアピールポイントになる
求職者が企業選びをする際、近年は給与や勤務地といった条件に加えて、「どのような働き方ができるのか」「休みが取りやすいか」といった視点が重要視されています。
採用サイトや求人票などに「夏季休暇有給制度あり(年3日)」と記載するだけでも、福利厚生をアピールできます。
特に中途採用や地方採用においては、福利厚生の充実度で最終的な判断をするケースも多いため、重要なアピールポイントになるでしょう。
まとめ

夏季休暇は労働基準法上の法定休暇ではなく、企業が就業規則などで自主的に定める「法定外休暇」に位置づけられます。
有給休暇とは法的な性質が異なり、給料の支払い有無や付与日数もすべて会社の裁量で決められます。
ただし、夏季休暇がない場合でも、従業員が年次有給休暇を利用して夏に休みを取ることは原則として認められており、正当な理由がなければ会社が却下することはできません。
制度としての夏季休暇を導入することで、従業員満足度の向上、生産性の向上、採用活動への好影響など、多くのメリットが期待できます。
ぜひ夏季休暇制度の導入・整備を検討してみてはいかがでしょうか。