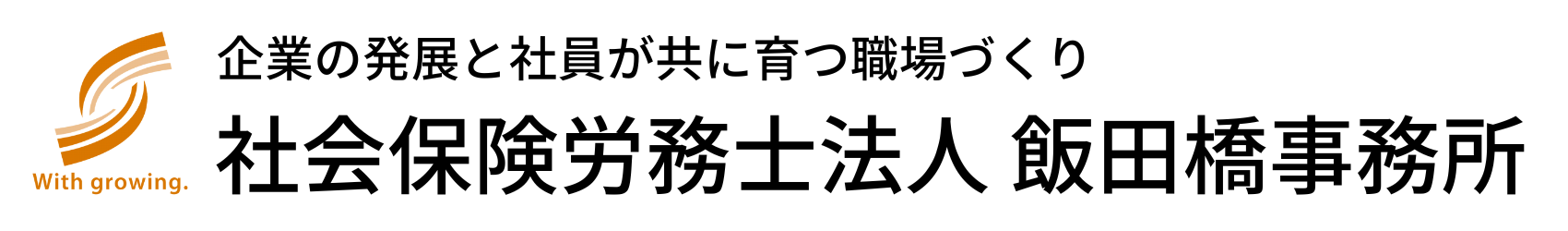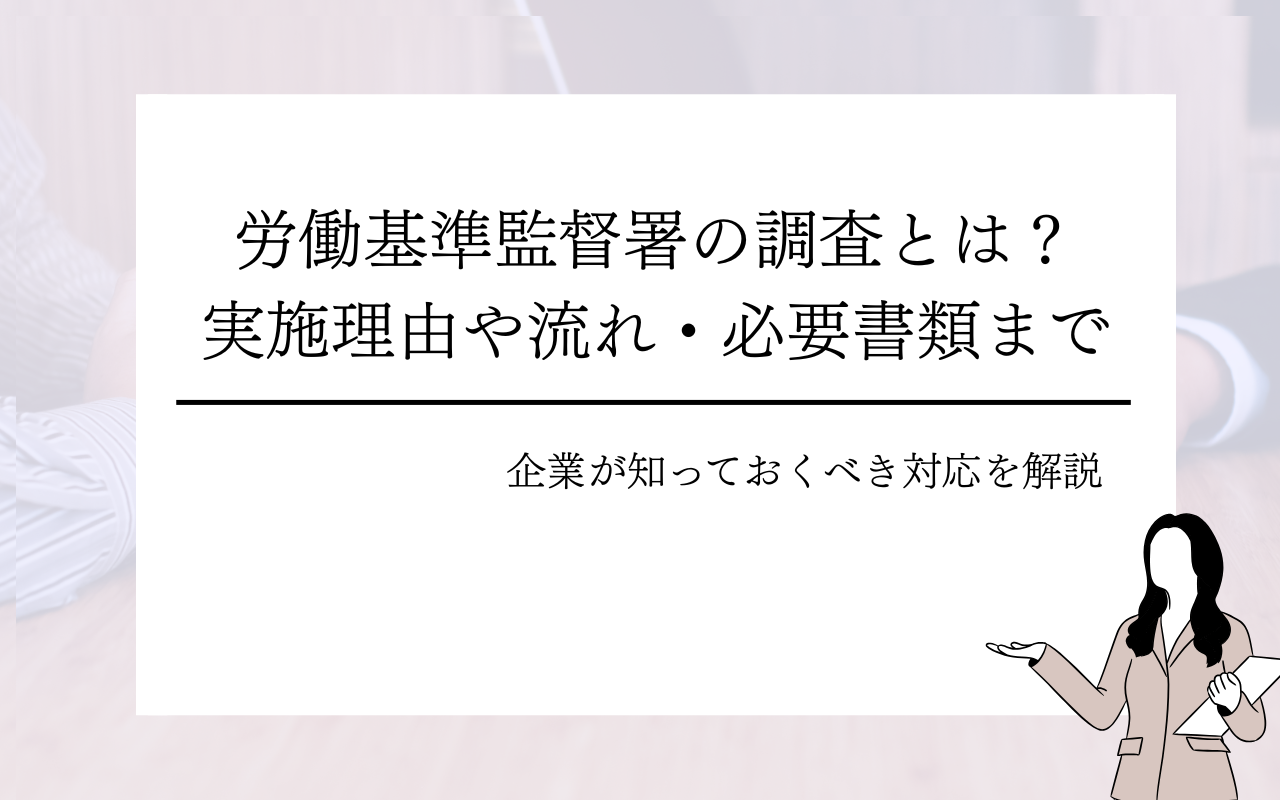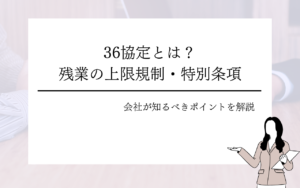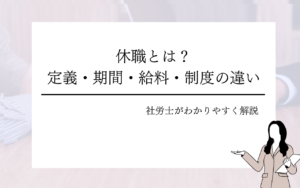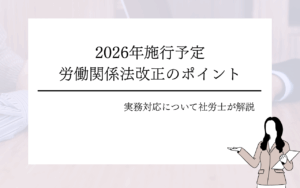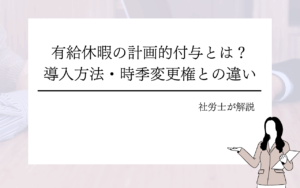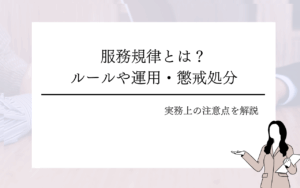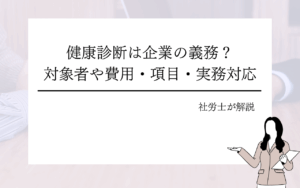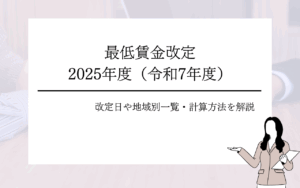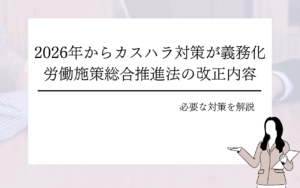労働基準監督署の調査は、突然の呼び出しや立ち入りがありえるため、不安を感じる経営者や人事・労務担当者も少なくありません。
調査では労働時間や賃金管理・有給休暇の付与状況・健康診断の実施など、幅広く確認されるため「自社の体制に不備はないか」と不安に思うこともあるでしょう。
そこで重要になるのが、調査の種類や流れ・必要書類を正しく理解し、事前に準備しておくことです。
本記事では、労働基準監督署の調査の目的や種類・流れ・必要となる書類から、指摘を受けた際の対応方法まで、企業が押さえておくべきポイントを解説します。
労務管理に不安を抱える方は、ぜひ最後までご覧ください。
労働基準監督署の調査とは

労働基準監督署の調査は臨検監督とも呼ばれ、労働者を守るために企業の労務管理体制を確認することを指します。
法律に基づいて実施されるもので、企業規模を問わず対象となります。
調査の目的や法的根拠、そしてどのような企業が対象となるのか詳しく見ていきましょう。
調査の目的や法的根拠
労働基準監督署の調査は、企業が「労働基準法」「労働安全衛生法」「最低賃金法」などの労働関係法令を守っているかどうかを確認するために行われます。
突然調査が入ることも珍しくなく、予告しなくとも、監督官には事業場への立ち入りや帳簿の確認、関係者への質問を行う権限が労働基準法第101条で認められています。
調査の目的は、法令違反を摘発することではなく、是正勧告・指導を通じて労働環境を改善し、労働者の健康や安全を守ることです。
そのため、企業は処分を恐れるのではなく、労務管理体制を日頃から整備し、不備がある場合にはすぐに対応することが大切です。
調査の対象となる企業
労働基準監督署の調査は、企業規模を問わず、労働者を雇用するすべての企業が対象です。
特定の業種だけが選ばれるわけではなく、通報や申告があれば小規模事業者でも調査を受ける可能性があります。
また、長時間労働が常態化している企業や労災が発生した事業場は、その後、重点的に調査されやすくなります。
ただ、規模にかかわらず調査は実施されるため、日頃から労務管理を適切に行う必要があります。
労働基準監督署の調査の種類
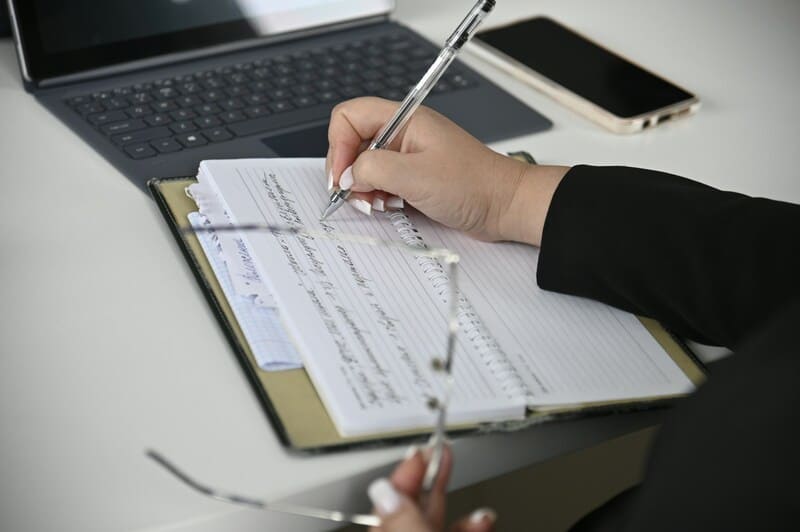
労働基準監督署の調査にはいくつかの種類があり、それぞれ実施される背景や目的が異なります。
突然の呼び出しや立ち入りがあった場合でも、どの調査に当たるのかを理解しておくことで、落ち着いて対応することができます。
それぞれの調査について見ていきましょう。
定期監督:計画的に行われる調査
定期監督は、労働局が策定する年間の監督計画に基づいて行われる調査です。
対象となるのは、行政の重点課題に関わる企業で、予告なく実施されることが多いのが特徴です。
例えば、長時間労働や過労死が社会問題となっている年には、労働時間管理を重点的に確認する定期監督が増える傾向があります。
申告監督:労働者からの通報による調査
申告監督は「未払い残業代がある」「パワハラを受けている」などの通報を受けた場合に、該当企業に対して実施される調査です。
調査は個別の申告内容に基づいて進められるため、特定の書類や労務管理の実態を詳細に確認されることが多いです。
通報内容が具体的で証拠もある場合には、企業は厳しい是正を求められることがあります。
不満やトラブル・法律違反を放置してしまうと、申告監督に発展するリスクがあるため、日頃から労働環境を整備することが大切です。
災害時監督・再監督などその他の調査
重大な労働災害や死亡事故が発生した場合に行われるのが、災害時監督です。
現場の安全管理体制や事故の原因を調べ、再発防止のための是正指導が行われます。
また、是正勧告を受けた企業に対して、その改善状況を確認する再監督が行われることもあります。
改善が不十分な場合、行政処分や司法手続きに発展するリスクもあるため、問題を放置せず確実に対応しましょう。
労働基準監督署の調査が行われる理由

労働基準監督署の調査は、企業を無作為に選んで行われるわけではありません。
多くの場合、労働者の申告や労災の発生など、何かのきっかけがあって実施されます。
ここでは、代表的な調査理由を紹介します。
通報や申告
労働者や元従業員などから「残業代が支払われていない」「有給休暇が取れない」などの申告があった場合、労働基準監督署はその内容を確認するために調査を行います。
申告内容が具体的かつ信憑性が高いと、調査の対象となる可能性が一気に高まります。
特に退職者からの申告は感情的なしがらみが少なく、信憑性が高いと判断されやすいです。
長時間労働・労災・パワハラ事案への対応
長時間労働が常態化している企業は、重点的な調査対象になりやすい傾向があります。
過労死ラインを超える残業(1ヶ月に100時間、2〜6ヶ月の平均が80時間以上)が続いていると、労働局の指導対象となり、調査に発展する可能性が高いです。
また、労災事故や死亡事故が発生した場合には、労働基準監督署が災害時監督を行い、原因究明や再発防止のための是正指導を行います。
さらに、職場でのパワハラやいじめがきっかけで調査につながるケースも増えています。
最低賃金・健康診断など制度的チェック
最低賃金を下回っていないか、有給休暇を適切に付与しているかといった基本的な労務管理も調査対象です。
また、労働安全衛生法に基づき、定期健康診断やストレスチェックの実施状況が確認されることもあります。
形式的に実施していても記録が残っていないと指摘を受ける可能性があるため、関連書類を適切に管理しておきましょう。
労働基準監督署の調査の流れ
労働基準監督署の調査は、呼び出し調査や立ち入り調査など複数のパターンがあります。
いずれの場合も、書類の確認から労働環境の聞き取り、是正指導まで一定の流れがあります。
ここでは、一般的な調査の流れを見ていきましょう。
予告の有無と調査方法の違い
調査は事前に書面などで連絡がある場合もありますが、予告なしで行われる場合も多いです。
呼び出し調査の場合は、会社に文書が届き、指定の日時に労働基準監督署へ書類を持参して説明を求められます。
一方で、立ち入り調査は、監督官が直接事業場に訪れ、帳簿や書類の確認、従業員への聞き取り、現場視察などを行います。
調査当日・そのあとの流れ
調査当日は、まず監督官から調査の目的や対象範囲について説明されます。
その後、労働時間や賃金・就業規則などに関する書類が確認され、必要に応じて担当者や従業員への聞き取りが行われます。
調査が終わると、その場で指摘事項が伝えられることもありますが、後日「是正勧告書」や「指導票」といった文書で正式に通知される場合もあります。
また、労働者の安全を脅かす緊急性を要する状況の場合には、法的拘束力を持つ使用停止等命令書が交付される場合もあります。
違反が重大な場合には、書類送検など法的措置が取られる可能性もあるため、誠実な対応が欠かせません。
調査で確認される内容と必要書類

労働基準監督署の調査では、労働時間や賃金管理・労災防止・安全衛生体制など、企業の労務管理全般が対象となります。
その際には、実態を裏づける証拠として、書類の提出を求められるのが一般的です。
ここでは、主に確認される内容と、代表的な必要書類を紹介します。
労働時間・賃金・有給休暇の管理(36協定届など)
労働時間の管理状況は、調査でも、特に重視される項目です。
タイムカードや勤怠管理表・出勤簿などの客観的な記録をもとに、労働時間が正しく把握されているかが確認されます。
さらに、時間外労働や休日労働を行わせる場合には、労使間で締結した36協定届(時間外・休日労働に関する届け)の提出が必要です。
賃金台帳や給与明細についてもチェックされ、割増賃金や最低賃金の状況、有給休暇の取得実績などが確認されます。
労災防止・安全衛生体制(健康診断結果など)
労働安全衛生法に基づく体制が、適切に整備されているかも重要な調査ポイントです。
産業医の選任や衛生委員会の設置が必要な事業場では、その体制が整っているかどうかを確認されます。
また、労働者に対して定期健康診断を実施しているか、その結果を適切に保管しているかもチェックされます。
健康診断を実施していない、あるいは記録が残っていない場合は、是正勧告につながる可能性が高いです。
就業規則・労働契約書の整備(労働条件通知書など)
就業規則が最新の法改正に対応しているか、労働基準監督署へ届け出がされているかも調査で確認されます。
労働契約書や労働条件通知書については、労働者ごとに正しく作成され、労働条件が明示されているかどうかが重要です。
特に、契約社員やパート・アルバイトなど非正規雇用者についても、書面で条件が明確に示されている必要があります。
就業規則や労働条件通知書に不備があると、是正の対象となりやすいため注意が必要です。
調査結果に対して企業の取るべき対応
調査が終わると、監督官から指摘事項が伝えられる場合があります。
その内容は「是正勧告書」や「指導票」といった文書で正式に通知され、企業には改善を求められます。
ここでは、調査後に企業が取るべき対応について解説します。
是正勧告書や指導票を受け取った場合の対応
そのため、まずは内容を確認し、指摘事項に沿った改善計画を立てることが必要です。
改善内容が不十分と判断されれば、再監督が行われることもあるため、誠実に対応しましょう。
調査を拒否・放置した場合のリスク
調査そのものを拒否したり、是正勧告を無視したりすることは大きなリスクを伴います。
そもそも事業主は調査を拒否することはできず、仮に拒否した場合には、悪質と判断され、労働基準法違反として書類送検・刑事罰の対象となることもあります。
また、企業の信用低下や取引停止など社会的な影響も避けられません。
「放置すれば済む」という考えは通用しないため、必ず誠実に対応しましょう。
調査に備えて企業がするべき実務対応

労働基準監督署の調査は、予告なしで行われることもあるため、その場しのぎの対応では限界があるでしょう。
普段から労務管理を適切にしておくことで、調査に対しても落ち着いて対応できるようになります。
ここでは、企業が事前に取り組んでおくべき実務対応を紹介します。
日常的な労務管理の整備
調査で確認される労働時間や賃金管理、有給休暇の付与状況は、日常的に正しく管理しておく必要があります。
タイムカードや勤怠管理システムを活用し、労働時間を客観的に記録する仕組みを整えることが重要です。
また、賃金台帳や年次有給休暇管理簿は記録を漏れなく保存し、いつでも提示できるようにしておく必要があります。
日常の積み重ねが、調査への不安を軽減する最大の対策となります。
社労士など専門家との連携
労務管理は法改正の影響を受けやすく、社内だけで完全に把握するのは難しく、見落としが起きる可能性も高いです。
社会保険労務士などの専門家と顧問契約を結んでおけば、最新の法令対応や書類整備を安心して任せることができます。
調査時に専門家が同席することで、監督官とのやり取りがスムーズになり、不要な誤解やトラブルを避けられる点も大きなメリットです。
抜き打ち調査にも対応できる体制づくり
労働基準監督署の調査は、予告なしに実施される立ち入り調査が多いのが実情です。
そのため「いつ来られても困らない」状態を維持することが理想です。
社内規程や書類を最新の状態に保つことに加え、担当者が不在でも対応できるよう、必要書類の保管場所や対応を共有しておくと安心でしょう。
抜き打ち調査への備えができていれば、万が一、勧告や指導を受けても、調査後の是正対応がスムーズに進められます。
まとめ
労働基準監督署の調査は、通報や長時間労働、労災などをきっかけに実施され、予告なしで行われることも多いです。
労働時間や賃金管理・健康診断の実施状況・就業規則や契約書の整備などが確認され、36協定届や賃金台帳といった書類の提出も求められます。
是正勧告を受けた場合でも、期限内に報告書を提出し誠実に改善すれば大きな問題には発展することはありません。
日頃から労務管理体制を整え、社労士など専門家と連携しておくことがおすすめです。