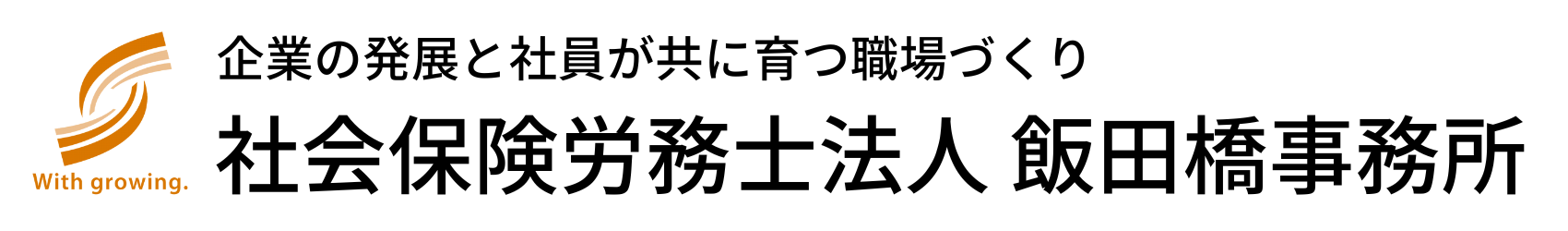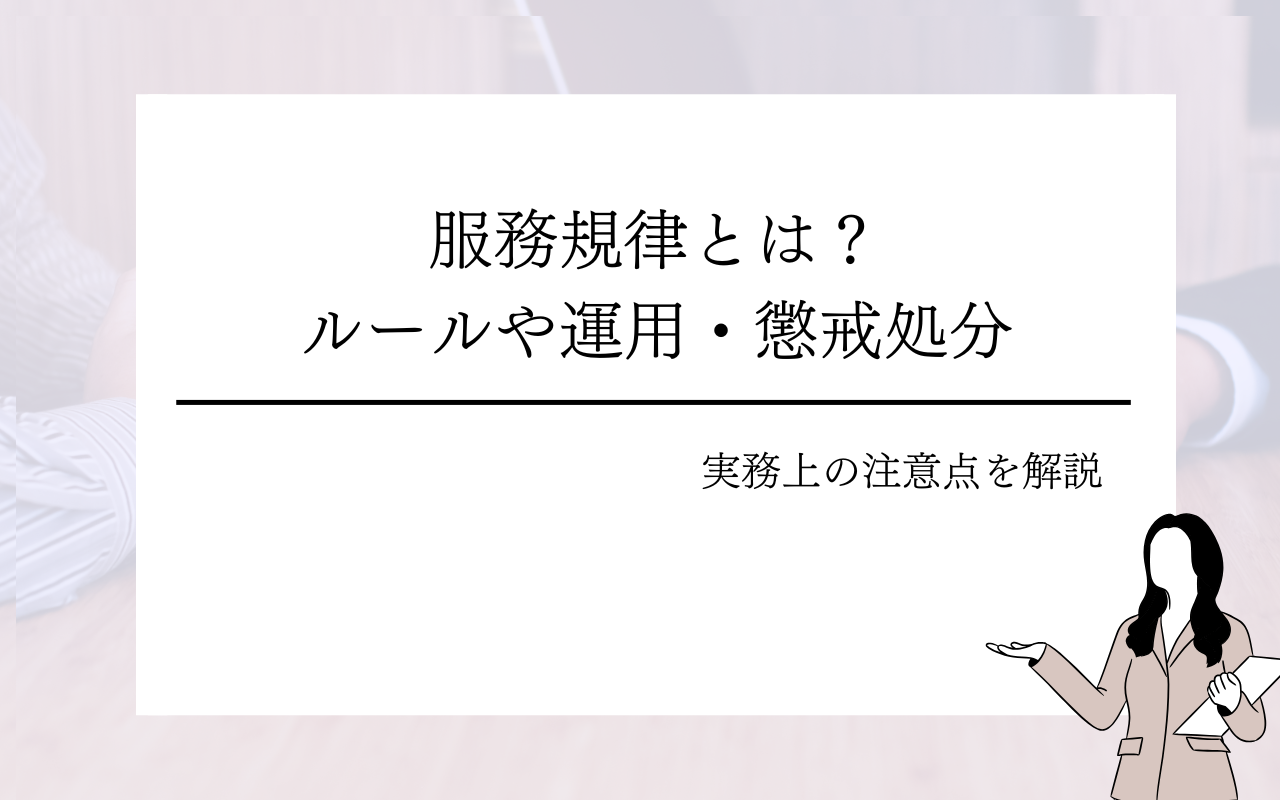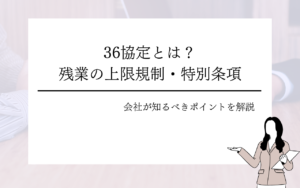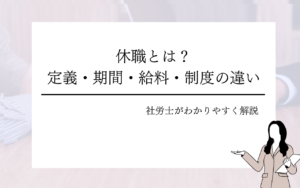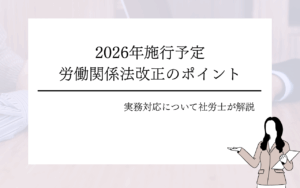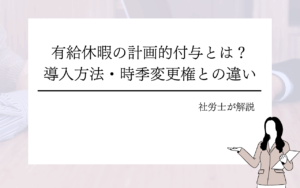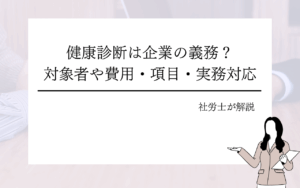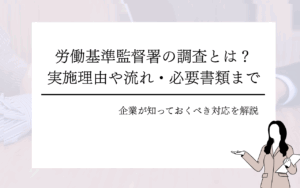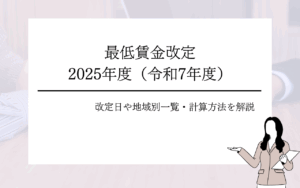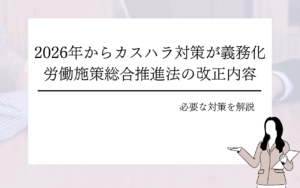服務規律は、企業が職場の秩序を保ち円滑な業務運営を行うために定めるべき「行動ルール」の1つです。
しかし、「どこまで定めればいいのか」「違反時の懲戒処分はどう扱うべきか」と悩む企業も少なくないでしょう。
そこで本記事では、服務規律の基本的な考え方から、定めるべき内容、運用・懲戒処分時の注意点までを社労士が実務目線でわかりやすく解説します。
服務規律について知りたい方や自社のルールを見直したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
服務規律とは何か

服務規律は、従業員が企業で働くうえで守るべき「行動のルール」を定めたものです。
単に服装や挨拶などのマナーにとどまらず、勤怠・職務遂行・情報管理といった幅広い領域にわたります。
まずは、服務規律の定義や目的・就業規則との関係など、基本的な位置づけを整理しておきましょう。
服務規律の定義と目的
服務規律とは、従業員が会社で働くうえで守るべき、基本的な行動基準を定めたものです。
勤務態度・職場での言動・会社の信用保持など、日常的な行動ルールを具体的に示すことで、職場秩序の維持やトラブル防止を図る目的があります。
法令上の明確な定義はないものの、労働契約法第3条や民法の信義則を根拠として、職場秩序を維持するために策定することが認められています。
服務規律と就業規則の関係・違い
服務規律は、一般的に就業規則の一部に位置づけられます。
就業規則が「労働条件や制度の全体像」だとすれば、服務規律は「日々の行動や態度」を定める部分です。
例えば、就業規則では「勤務時間は9〜18時」と定め、服務規律では「始業時刻までに着席して業務の準備を行う」といった内容です。
服務規律は就業規則の運用を支える実務的ルールとして機能し、明確に定めておくことで「曖昧な基準による注意・処分」といったトラブルを防ぐ効果があります。
服務規律を就業規則内で十分に具体化しておくことが、労務関係のリスクを減らすうえで欠かせません。
服務規律が企業運営・秩序維持に果たす役割
服務規律という形でルールを明確にすることで、指導や懲戒を行う際にも客観的な判断基準を示すことが可能です。
また、服務規律の存在は、社外から見た企業の信用にも影響します。
近年はSNS投稿や情報漏えいなど、社外での行動によるトラブルも増加傾向にあります。
従業員が服務規律を理解し、日常的に意識して行動することで、会社のブランドや顧客との信頼関係を守ることができるのです。
「服務規律=組織のコンプライアンス基盤」と捉えてもよいでしょう。
服務規律で規定すべき主なルール
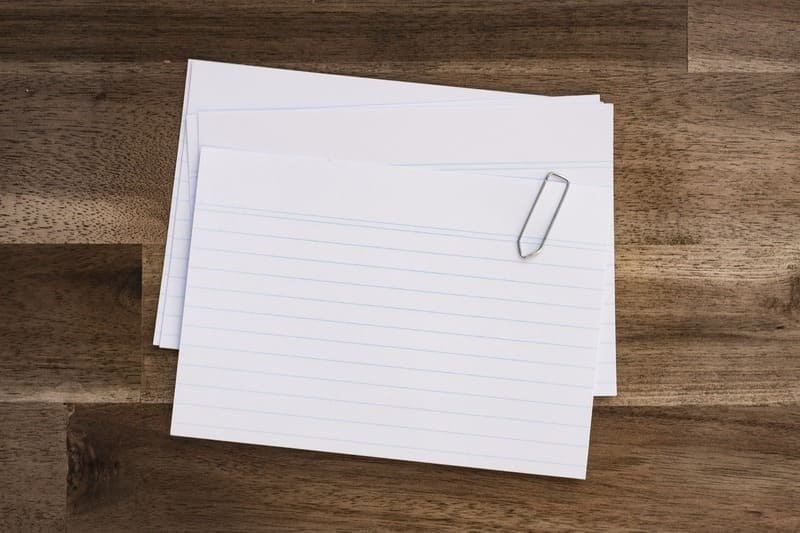
服務規律は、従業員が「何をしてはいけないか」「どのように行動すべきか」を明確に示すルールです。
抽象的だと解釈の違いからトラブルを招き、逆に細かすぎると現場の柔軟性を損なうおそれもあります。
以下では、服務規律に盛り込むべき項目や具体例を整理し、自社の業種・文化に合ったルール設計についてみていきましょう。
服務規律に盛り込むべき基本項目
服務規律を定める際は、従業員の勤務態度や日常行動に直結する内容を盛り込みましょう。
主な項目としては、以下の項目が挙げられます。
- 勤務態度・職務専念義務
- 命令遵守
- 守秘義務
- 身だしなみ
- 会社財産の管理
- 服装・身だしなみ
- ハラスメント
- 競業避止義務
- 副業・SNS
まずは自社で「最低限守るべき行動」を明確にすることから始めましょう。
禁止事項・遵守事項の具体例
服務規律では、具体的な禁止・遵守行為を例示することが重要です。
例えば「無断欠勤をしない」「会社の信用を損なう行為をしない」「機密情報を外部に持ち出さない」「勤務中の私用スマートフォン使用を控える」といった内容です。
さらに、SNSでの発言や情報管理など、近年増えているリスクも考える必要があるでしょう。
企業文化や職種に応じたルールの考え方
服務規律は、企業の業種や職種によっても重点を置く内容が異なります。
例えば、製造業では「安全手順の遵守」や「私語・スマホ操作の禁止」など、接客業では「言葉遣い」「顧客対応時の身だしなみ」などが重要視される傾向にあります。
自社の事業特性を踏まえて、「どのリスクを防ぐために何を定めるのか」を明確にすることが大切です。
また、事業の特性だけでなく、企業理念や行動指針と連動させることも必要でしょう。
服務規律違反に対する懲戒処分とは
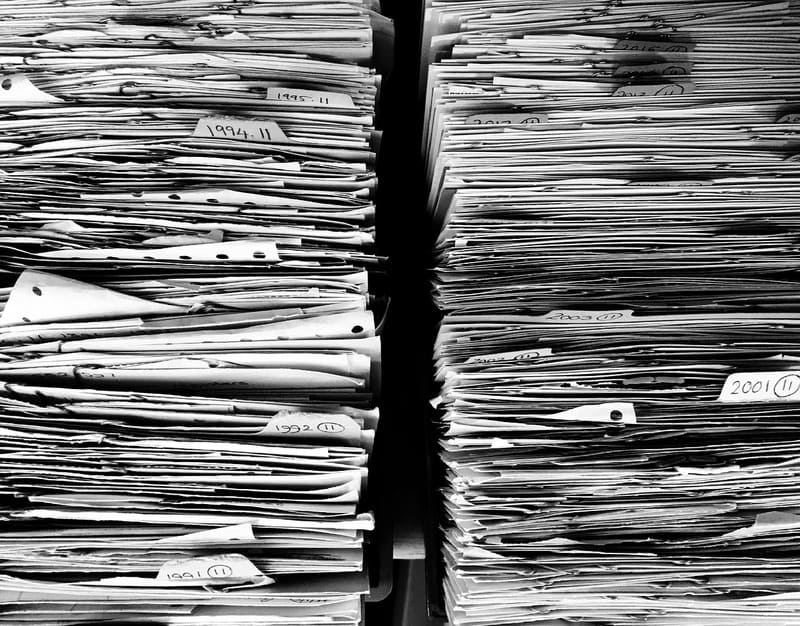
服務規律に違反した場合、会社は懲戒処分を科すことができます。
ただし、懲戒処分はあくまで職場秩序の維持を目的とするもののため、不適切な対応は「懲戒権の濫用」と判断される可能性があります。
懲戒処分の種類や処分の重さを判断基準を整理し、実務トラブルを防ぐためのポイントを整理しましょう。
懲戒処分の種類と法的根拠
懲戒処分とは、従業員が服務規律や就業規則に違反した場合に、会社が秩序維持のために行う制裁措置を指します。
主な種類は次のとおりです。
- 戒告・譴責:注意や反省を促す最も軽い処分
- 減給:1回の減給は1日平均賃金の半額以内、総額で1賃金支払期の1/10以内
- 出勤停止:一定期間の就労義務を停止する
- 降格・降職:役職や等級の引下げ
- 諭旨解雇:本人に反省を促し自主退職を勧告
- 懲戒解雇:最も重い解雇処分で退職金不支給などが伴う場合もある
懲戒処分は就業規則に、明記されていなければ行えません。
明示せずに処分を行うと、後に無効と判断される可能性があります。
服務規律違反を理由に懲戒処分を行う際の要件
懲戒処分を有効に行うには、以下4つの要件を満たす必要があります。
- 就業規則で懲戒処分の根拠が明文化されている
- 懲戒処分に値する事実がある
- 懲戒処分の内容が社会通念上相当である
- 適正手続を経ている
まず、就業規則に違反行為が明示されていること、その行為が事実としてあることが前提です。
その上で、社会通念上相当といえる処分であることが求められます。
また、上記の要件に加えて、当事者に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを踏まなければなりません。
これらを怠ると、「懲戒権の濫用」と判断されるおそれがあり、処分無効だけでなく損害賠償請求につながるケースもあります。
懲戒を検討する際は、感情的な判断を避け、客観的な事実と証拠に基づいて冷静に対応することが重要です。
処分の重さを決める判断基準
懲戒処分の量定(重さ)を決める際には、以下の要素を考慮しましょう。
- 違反行為の内容や悪質性(故意か過失か)
- 業務や他者への影響の大きさ
- 本人の勤務態度や過去の指導歴(注意しても何度も繰り返していないか)
- 同種事案の過去の対応歴(他の従業員との公平性)
- 社会通念上の相当性
例えば、初めての遅刻や報告漏れに対して重い処分を行うのは相当ではありません。
一方で、無断欠勤や情報漏えいなど重大な行為については、会社を守る観点から厳正な対応が求められます。
懲戒処分は、組織の秩序を守るための手段として慎重に運用することが大切です。
服務規律の運用|実務上の注意点
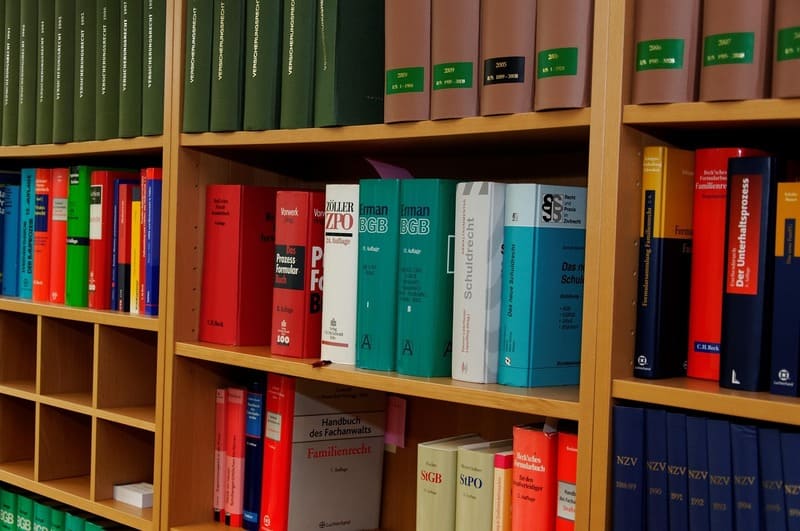
服務規律は、定めただけでは十分とはいえません。
運用の仕方を誤ると、従業員とのトラブルや懲戒処分の無効など、思わぬリスクを招くことがあります。
以下では、服務規律の運用ポイントを3つの観点から解説します。
トラブル防止のための周知・教育体制
服務規律を有効に機能させるには、従業員への周知と理解が不可欠です。
就業規則や社内規程を配布するだけでは「周知義務」を果たしたとはいえません。
入社時の説明会や研修で具体的な事例を交えながら説明し、従業員が自分ごととして理解できる環境を整えることが大切です。
また、ハラスメントやSNSに関するルールなど、状況に応じて変化するテーマについては定期的な周知・教育を実施しましょう。
「知らなかった」と言われない状態を作ることが重要です。
服務規律変更時の注意点【不利益変更の回避】
服務規律の見直しを行う際には、従業員にとって不利益とみなされる変更が含まれる場合、労働契約法第9条・第10条に基づく「合理性・周知性の確保」が必要です。
例えば、私用スマートフォンの持ち込み禁止や服装ルールを厳格化する場合には、業務での必要性や社会通念上の妥当性が求められます。
変更の理由や背景を説明し、従業員の代表から意見を聴取するなど、手続きを丁寧に進めることでトラブルを防げます。
特にSNS・副業・在宅勤務など新しい働き方に対応する際は、不利益変更に該当しないよう、慎重に対応しましょう。
懲戒処分の無効・濫用を防ぐためのポイント
服務規律違反に対して懲戒処分を行う場合、運用方法を誤ると処分自体が無効になるおそれがあります。
懲戒処分を行う際は、まず事実関係を客観的に確認し、本人に弁明の機会を与えるなど、適正な手続きを踏むことが必要です。
また、過去の同種事案と同様の対応を取ることで「公平性」を担保します。
同じ行為に対して人によって処分の重さが異なると、社内の信頼を損なう原因にもなるため注意しましょう。
まとめ

服務規律は、従業員一人ひとりの行動を明確化し、職場の秩序や信頼を維持するための重要なルールです。
単にルールを設けるだけでなく、「どのように運用するか」「どこまで懲戒を適用するか」を明確にすることで、組織全体で公平性を守ることができます。
一方で、服務規律や懲戒の内容は、企業ごとに適切な水準が異なります。
ルールづくりや見直しを進める際は、法的なリスクを踏まえて慎重に進めることが大切です。
「服務規律の内容を見直したい」「懲戒処分を検討しているが判断に迷う」という場合には、専門家である社労士への相談がおすすめです。
第三者の視点で制度設計を見直すことで、社内のトラブル防止だけでなく、従業員からの信頼向上にもつながります。
自社に即した服務規律の整備・運用を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。