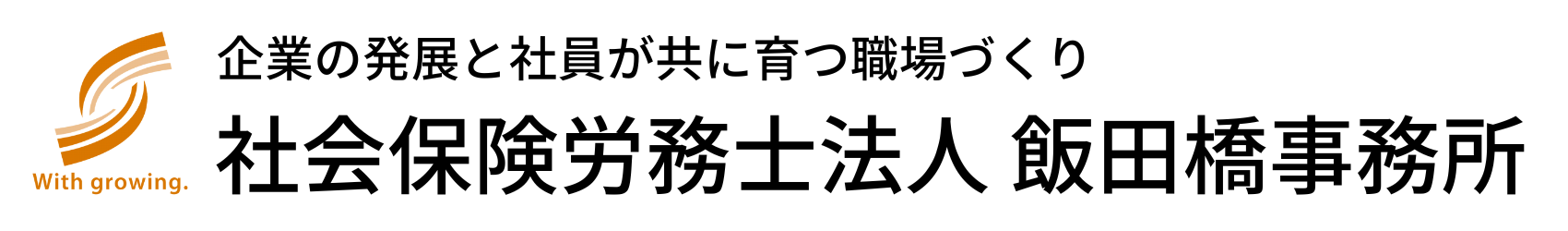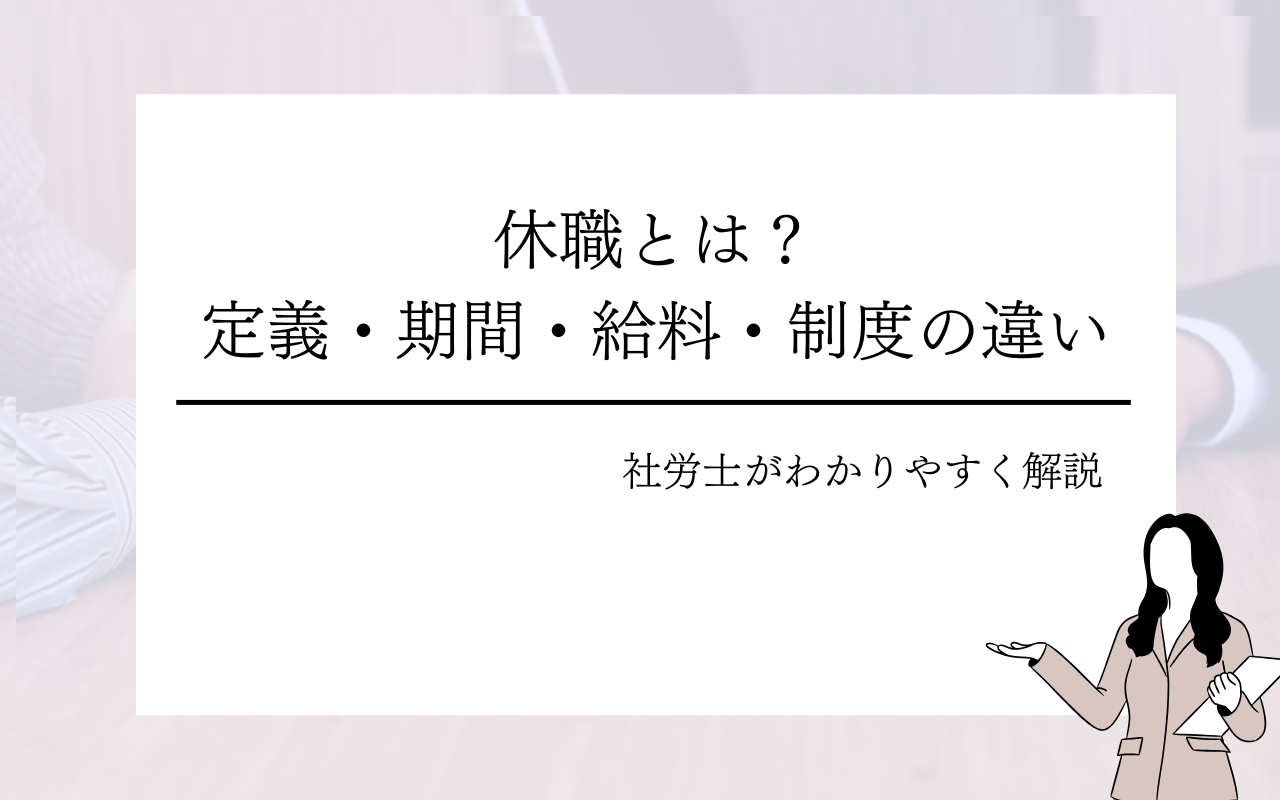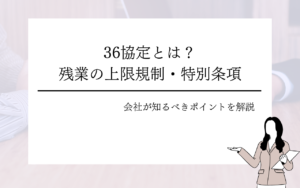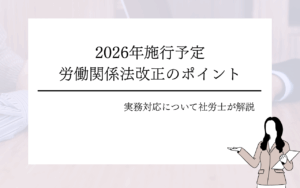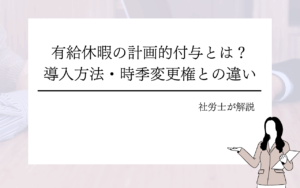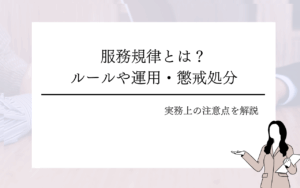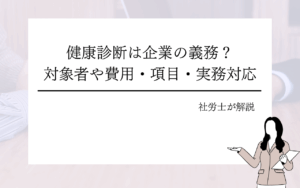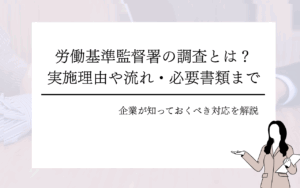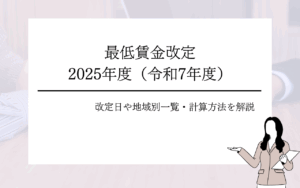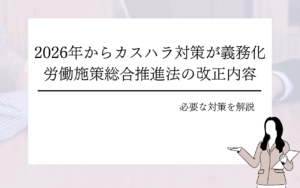従業員が体調不良やメンタルの不調で長期間働くことができなくなった場合、会社としてどのように対応すべきか、迷う場面は少なくないでしょう。
「休職」と聞くと「一定期間仕事ができない、労務を提供できない何らかの理由があり休む制度」といったイメージを持つ方も多いでしょう。
法的な定義があるものではないため、会社ごとに就業規則で定めて運用する制度といえます。
そのため正しい理解と適切な運用が欠かせません。
本記事では、休職制度の定義や法的な位置づけをはじめ、期間・給料・社会保険の取り扱いなどについて、社労士の視点からわかりやすく解説します。
「社員から診断書が提出された」「休職期間の設定に悩んでいる」といった企業の方は、ぜひ最後までご覧ください。
休職とは

従業員が心身の不調などで、長期間勤務することができなくなった場合に活用されるのが「休職制度」です。
実は、休職は法律で明確に定められた制度ではなく、各企業が就業規則で自主的に定める制度です。
まずは、休職の定義や法的な位置づけを整理し、類似する制度との違いを押さえておきましょう。
休職の定義と法的な位置づけ
「休職」とは、従業員が病気やけが・メンタル不調などの理由で長期間にわたって働くことができない場合に、一定期間、労働義務を免除しつつ雇用関係を維持する制度です。
ここで押さえておきたいのは、労働基準法などの法律に「休職」について明確な定義が存在しないことです。
休職制度は、各企業の就業規則を根拠として自主的に定める任意の制度です。
多くの企業では、就業規則の中で「私傷病」「留学」「公職就任」など、休職の対象や期間・復職手続きなどを定めています。
休職制度は、従業員にとっては、労務の提供ができない状態になったことですぐ退職となる状況を回避し、療養に専念することができる期間となりますし、会社にとっては育成した人材を失うといったリスクを回避することにつながります。
先述のとおり、休職制度は会社で必ず定めないといけない、といった法的義務はありませんが、労働契約法第5条(安全配慮義務)の観点から、適切な制度設計と運用が求められます。
休業・育児休業・産休・介護休業との違い
「休職」は「休業」と混同されがちです。
「休業」は、会社の都合で働くことができない状態(災害・経営悪化など)を意味し、会社に賃金の支払い義務が生じるケースもあります。
休職期間については、中小企業では無給と定めていることが多いです。そのため、給与を受けることができない期間の生活保障として、健康保険法の傷病手当金を申請し受給することとなります。
なお、育児介護休業法に定める育児休業、介護休業、労働基準法に定める産前産後休業は、いずれも法律に基づく「法律上の休業制度」のため、会社は原則として従業員からの申し出を拒否することができません。
対して休職は、会社が独自に定める任意の制度であり、会社が発令して開始するものです。
ここが最大の違いといえるでしょう。
年次有給休暇との関係
休職と年次有給休暇の関係も整理しておきましょう。
体調不良などで労務の提供が難しい場合、いきなり休職制度をスタート、というよりもまずは年次有給休暇を消化し、それでもまだ復帰が難しい場合に欠勤で様子見をすることが一般的といえます。
しばらく欠勤をしてもなお復帰が難しいと言った場合に、いよいよ「休職制度」へ移行するケースが多いです。
休職期間中は、ノーワーク・ノーペイの原則により、中小企業では無給で規程することが一般的です。
休職期間中は年次有給休暇を取得することができない、という点に注意が必要です。なぜなら休職期間は会社から「労務提供の義務が免除された期間」にあたるためです。
会社としては、休職制度の開始日を明確にすることがのちのトラブルを抑止することになります。どこまでが年次有給休暇なのか、欠勤なのか、休職期間の開始なのかを明確にしましょう。
そのためには、休職制度の開始前に必ず休職辞令(通知書)を発行することをおすすめいたします。
休職の主な理由と種類

従業員の意向による休職の開始として多い理由は「私傷病による休職」です。
休職は年次有給休暇のような、従業員が取得したいと希望をすればできるもの、ではなく会社が従業員の状況から労務の提供が難しいのではないかと判断した場合に「会社が発令して従業員を休職させる制度」といえます。
会社が命じるものですので、会社は通知書を発行する、という流れになります。
ここでは、会社が休職を命じる・本人の意向を受けて休職を開始するにあたって想定される主なケースを整理して、業務上の災害など他の制度との違いもあわせて確認しましょう。
私傷病(病気・けが)による休職
休職理由として最も一般的なのが、業務外で発生した病気やけがなどのいわゆる私傷病による休職です。
私傷病による休職は、従業員が治療や療養に専念するために一時的に会社を休むことを指しますので、雇用関係は継続します。
会社は就業規則で「どの程度の期間勤務できない場合に休職とするか」を定めておく必要があります。
例えば「欠勤が連続して1か月を超えたときに欠勤の開始日を休期間の始期とする。」など、明確な期間を記載することで公平性と透明性を確保できます。
業務上災害による休業との違い
「業務中のけが」や「通勤途中の事故」は、労災保険の対象となるため、「休職」ではなく労災による休業として扱われます。
休業中の生活保障として労災保険法から「休業補償給付」または「休業給付」の支給が受けられるため、会社は休業した期間の給与については無給とすることが多いといえます。
一方、私傷病休職は業務外の理由によるものですので、健康保険法の「傷病手当金」を申請し支給を受けるケースが多いです。
どちらも国の制度による給付ですが、休業となった「原因」や「理由」によって、労災で処理するか、健康保険で処理するかが異なってきます。
同じメンタルヘルスの不調(うつ病など)という理由であっても、原因が業務上なのか、業務外であるのかによって給付をする行政機関が異なりますので注意が必要です。
長時間労働や上司のハラスメントなど、業務上の強いストレスが原因で休業し、給与が支給されなかったため、労災として申請し、監督署が審査の結果労災であると判断した場合は労災保険の休業補償給付を受給することとなります。
一方、私生活に要因があるものであれば「私傷病休職」の扱いとなり、健康保険から傷病手当金の受給を検討することになるでしょう。
どちらに該当するかの判断が難しいケースもあり、誤った判断はトラブルや労災申請の遅れにつながるため、社労士など専門家への相談がおすすめです。
休職期間と復職の基本ルール

休職は、雇用関係を維持しながら労働義務を免除する制度です。
「どのくらいの期間を休職とするか」「期間満了後にどう扱うか」は、すべて就業規則で定めておく必要があります。
ここでは、休職期間の考え方や延長・復職判断の実務対応を整理して解説します。
休職期間は就業規則で定める
休職期間の長さは法令で決まっているわけではないため、会社ごとに就業規則で定める必要があります。
一般的には、勤続年数や職種に応じて、以下のような期間で定めるケースが多いです。
・3か月〜6か月(主に中小企業の場合)
・1年(主に大企業)
会社が任意に定める制度のため、企業の規模によって休職期間、給与を無給とするか一部支給とするかなど、考え方も異なります。
重要なのは、全社員に対して明確かつ公平に適用できる基準を設けることです。
また、休職期間満了時点で復職できない場合の取り扱いも、もれなく定めておく必要があります。
期間満了・延長・復職の判断基準
休職期間が満了しても、従業員の体調が完全に回復していないことはよくあります。
そのため多くの会社では、一定の条件をもとに延長を認める運用をしているケースが多いです。
ただし延長するかどうかについては、会社に判断する権限があり、医師の診断書等をもとに慎重に判断していくことになります。
復職の可否を判断する際は、主治医の意見書や産業医の面談結果・勤務実績などを総合的に考慮していくことになります。
復職が難しいときの判断としては、就業規則に「休職期間が満了しても復帰できないときは、満了日をもって自然退職とする。」という定めがあれば休職期間の満了をもって退職となります。
このような定めをしているケースが一般的といえます。
休職期間を延長する規定があれば、延長も検討することになります。
休職中の給料と社会保険

休職期間中の賃金や社会保険の取り扱いは、トラブルが発生しやすいポイントです。
「無給なのか」「社会保険料は会社も本人も負担する必要があるのか」「傷病手当金は申請すれば給付が受けられそうか」など、色々気になるところだと思います。
休職中の給与と社会保険の基本ルールについて見ていきましょう。
原則無給(ノーワーク・ノーペイ)
休職中は、従業員は働いていないため「ノーワーク・ノーペイ」の原則から、会社は給与を支払う義務がないため、一般的に給与の支給はなしと定めるケースが多いです。
ただし、会社によっては、独自に「休職手当」を支給する、または給与の一部を引き続き支給する制度を設けている場合があります。
なお、このような社内制度を導入する際は、
・対象者・支給期間・金額の基準
・給与の支給がある場合に傷病手当金が支給停止または一部減額になること
などについても説明する場を設けるなども検討すると良いでしょう。
給与が一部支給されることで、傷病手当金の一部減額や不支給に影響しますので、設計には注意が必要です。
傷病手当金の支給条件と仕組み
休職中の生活補償として活用されるのが、健康保険の「傷病手当金」制度です。
傷病手当金は、業務外のけがや病気で働けなくなった場合に、標準報酬月額の3分の2相当が支給される制度です。
支給を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.業務外の病気・けがであること
2.医師により「労務不能」と判断されていること
3.会社を連続3日以上休み、4日目以降も働けない状態であること
4.その間、賃金の支払いを受けていないこと
傷病手当金は、申請書に会社・被保険者・医師の証明欄を記入し、健康保険組合または協会けんぽに提出します。
なお、支給対象期間が長期化する場合は、申請書に毎回医師の証明欄に証明をもらう必要がありますので、どのくらいの期間を単位として申請するかもよく考えて行う必要があります。
社会保険料・税金・手当の扱い
休職中も雇用関係が続いているため、社会保険の被保険者資格は維持されます。
ただし、休職には産前産後休業、育児休業のような社会保険料免除の特例がないため、健康保険料や厚生年金保険料は原則として発生します。
また、住民税は特別徴収の場合は給与から控除しますので、休職期間が長期にわたる場合は特別徴収から普通徴収への切り替えも検討することになります。
所得税も支給額によっては控除となります。
会社としては、本人と住民税の徴収方法を変更する必要があるかどうか、面談で確認しましょう。
休職手続きと必要書類

休職は就業規則で定める任意の制度であるため、形式的な手続きが必要です。
合わせて休職辞令(通知書)を発行し、復職の検討には本人から医師の診断書の提出が必須となります。
ここでは、休職手続きの基本的な流れと、必要な書類・確認事項を整理します。
会社が休職辞令を発令するまでの流れ
一般的な休職の流れは、以下のとおりです。
1.本人が体調不良などの理由で休職制度の利用を希望している旨の相談を受ける
2.医師の診断書を会社に提出
3.会社が内容を確認し、休職の可否を判断
4.休職辞令(休職通知書)を発行し、本人へ交付
会社側は、提出書類の確認だけでなく、休職開始日や期間・給与の扱い・社会保険の取り扱いについても、事前に面談等で説明をすることが重要です。
診断書提出と産業医の確認
私傷病による休職の開始を判断するうえで重要なのが診断書です。
診断書には、医師が従業員の心身の状況と、労務の可否等を医学的に診断した内容が記載され、休職開始の妥当性を客観的に示す根拠となります。
本人のかかりつけ医の診断書の内容について会社の見解と齟齬がある場合は、産業医がいる場合は産業医の診察を受けてもらい、慎重に判断をすることとなります。
また、職場復帰を検討する段階でも、産業医による面談を行うのが望ましいと言われています。
休職中・復職時の実務対応

休職制度で重要なのは、制度の設計はもちろんですが、復帰に向けての休職中の対応、本人との連絡・報告の頻度と職場復帰にむけての支援です。
特に、休職中の従業員との関わり方や復職判断の方法は重要です。
実務的に押さえておきたい3つのポイントを整理して見ていきましょう。
休職中のフォローと連絡体制の整備
休職期間中は、従業員と会社のコミュニケーションが途絶えやすいですが、定期的に連絡や報告を受ける体制づくりは重要です。
本人の体調を尊重しつつ、月1回程度の近況報告や人事担当者との連絡を継続しましょう。連絡は「復職の催促」ではなく「状況の共有や支援」を目的とすることが大切です。
産業医や上司を交えた面談の場を設けることで、職場とのつながりを保ちながら安心して療養を続けてもらえるでしょう。
会社としては、復職や退職の判断を行う際の重要な資料になるため、連絡内容や面談結果を記録し、対応経過を文書で残しておくことが望ましいです。
復職判断・リハビリ出勤・配置転換の対応
復職の可否を判断する際は、主治医の診断書や産業医の意見・本人の意思を総合的に確認します。
「業務に支障なく復帰できるか」「勤務時間や業務内容に制限が必要か」を明確にし、場合によっては段階的に職場復帰させる方法も検討しましょう。
また、復職後に休職前の同一部署での勤務が難しい場合は、配置転換や職務内容の見直しも検討する必要があります。
復職不可時の対応と解雇リスクの管理
休職期間が満了しても復職できない場合には、「自然退職」「普通解雇」などの判断を迫られる場面が出てくるでしょう。
ここで注意すべきなのは、安易な解雇は無効と判断されるリスクが高いという点です。
労働契約法では、業務上・業務外を問わず、病気療養中の解雇は原則として制限されると定められています。
また、復職可否の判断が不十分なまま解雇した場合には、「不当解雇」としてトラブルに発展する可能性があります。
そのため、会社は必ず以下の項目を整理・保存し、合理的な手続きを徹底することが重要です。
1.医師の診断書と産業医の意見
2.本人との面談
3.復職困難と判断した理由
必要に応じて社労士や弁護士に相談し、トラブルを未然に防ぎましょう。
まとめ
休職制度は、労務の提供ができない状態になったことですぐ退職、となることを回避できる制度であり、従業員にとっては労務の提供義務が免除され、療養に専念することができる期間となります。
特に中小企業では、制度の内容が曖昧なまま運用されているケースも少なくありません。
もし、「自社の就業規則に休職条項を追加・改訂したい」「休職から復職までの流れを整備したい」といった課題を感じている場合は、ぜひ一度専門家にご相談ください。
社会保険労務士法人飯田橋事務所では、企業規模や業種に合わせた就業規則の設計・労務管理体制の整備をサポートしています。
実際の事例に基づいたアドバイスや制度設計の相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。