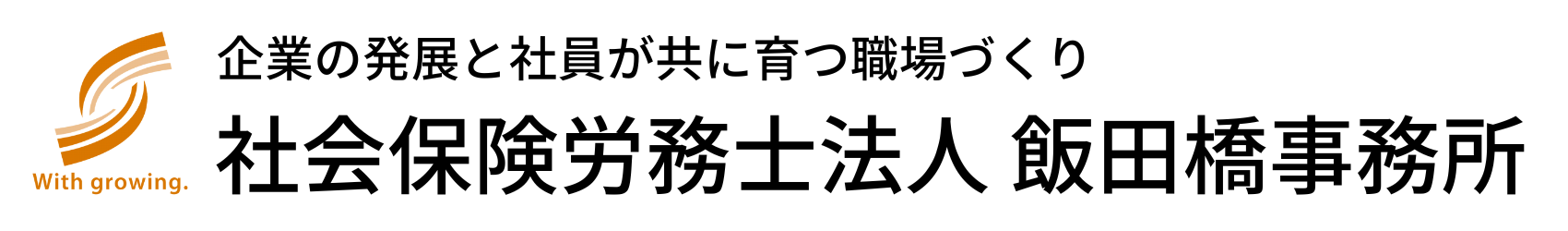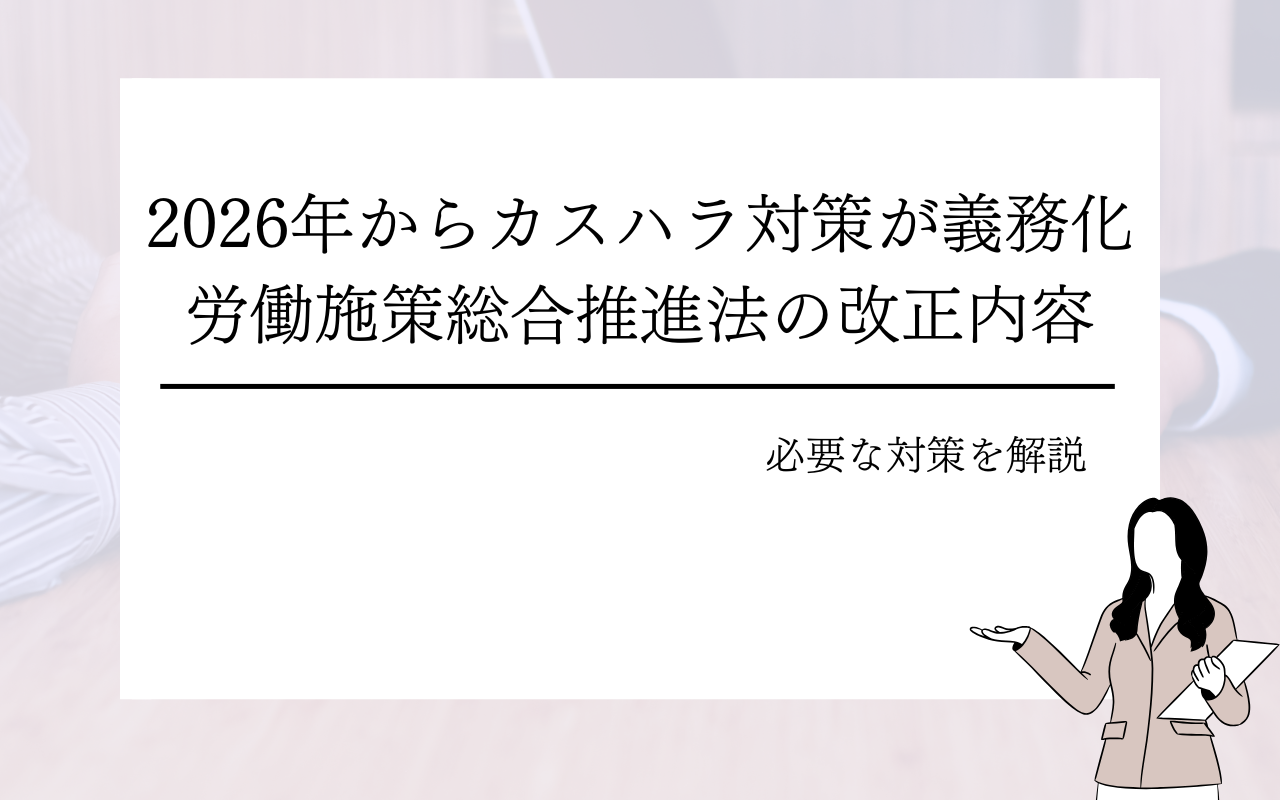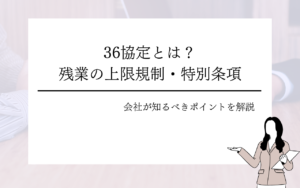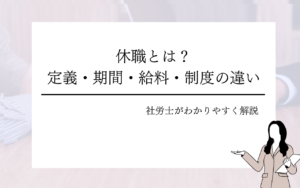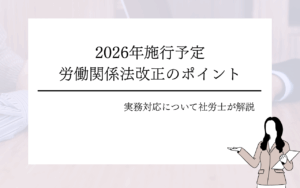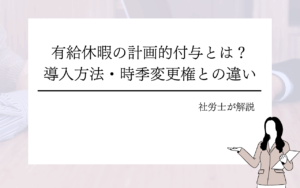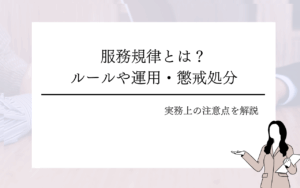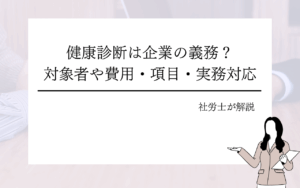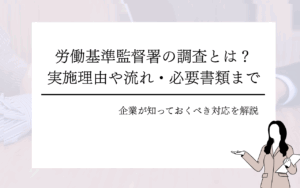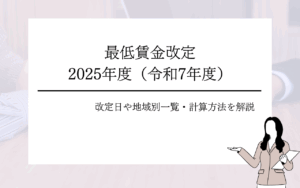「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉を耳にする機会が増えていませんか?
理不尽なクレームや暴言、過度な要求は、現場で働く従業員の心身に大きな負担を与え、離職や労働意欲の低下にもつながりかねません。
こうした背景を受け、セクハラ、マタハラ、パワハラに続き、2026年にはカスハラ対策が企業の義務として追加される予定です。
本記事では、労働施策総合推進法の改正内容や企業が取るべきカスハラ対策について、社労士の視点からわかりやすく解説します。
カスハラ対策に課題を感じている経営者・人事担当者の方は最後までご覧ください。
そもそもカスハラとは?企業が無視できない新たなハラスメント

「カスハラ(カスタマーハラスメント)」とは、顧客や取引先が従業員に対して行う過剰なクレーム・暴言・脅迫行為などの迷惑行為を指します。
厚生労働省はカスハラを「顧客等からの著しい迷惑行為」と定義しており、その深刻さは社会問題として年々注目を集めています。
たとえば、サービス業や医療福祉業では、「土下座の強要」「業務外の私的な要求」「長時間の威圧的な態度」など、従業員の尊厳を踏みにじる行為が報告されています。
これまで、企業は顧客満足を最優先とするあまり、従業員が理不尽な対応を強いられるケースも少なくありませんでした。
しかし、働き方改革や労働環境の改善が求められるなか、「お客様は神様」といった考え方は根本的に改める必要があります。
以下では、企業にカスハラ対策を義務化する背景と、2026年に予定されている法改正の内容について詳しくみていきましょう。
労働施策総合推進法改正とは?2026年に施行予定

2026年施行予定の「労働施策総合推進法」の改正により、カスタマーハラスメント対策が企業の義務となる予定です。
これまでも厚生労働省は事業主に、カスハラ対策をおこなうことを「望ましい取り組み」としていましたが、今回の改正では、一定の対応が義務となる点が大きな違いです。
セクハラ・パワハラと同様に、カスハラについても具体的な対応策を講じる必要があります。
では、なぜ今、カスハラ対策の義務化が求められるようになったのでしょうか。
カスハラ対策が義務化される背景
カスハラ義務化の背景は、主に3つのことが挙げられます。
1つ目は、カスハラ被害の深刻化です。
厚生労働省が公表した令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書によると、過去3年間にカスハラの相談有無で「有」と回答した企業は27.9%という調査結果になりました。
業種別でみると「医療・福祉」「宿泊業・飲食サービス業」「不動産業・物品賃貸業」の順で相談があったと回答した企業の割合が多いことが分かりました。
2つ目は、従業員のメンタルヘルスへの影響が深刻化している点です。
顧客からの暴言や過剰な要求は、うつ病や適応障害の原因となり、長期休職や離職につながるケースも多く見られます。
このような状態を放置してしまうと、生産性の低下や人材流出といった悪影響が企業にもでてきます。
3つ目として、従業員の人権意識の高まりが背景にあります。
企業が社会的責任(CSR)を果たすうえでも、カスハラ対策は不可欠といえるでしょう。
義務化の対象範囲|中小企業や自治体にも適用される?
原則として、労働者を雇用するすべての事業主が対象で、業種や規模を問わず、対策義務が課されることになります。
中小企業では、「対応リソースが限られている」「マニュアルがない」といった課題が想定されますが、実行可能な範囲での取り組みが求められます。
労働施策総合推進法の改正で企業に求められる対応

ここでは、カスハラの定義を確認しましょう。
「カスハラ」とは、以下の3つの要素をすべて満たすものを言います。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により
- 労働者の就業環境を害すること
具体的な内容については、今後指針で示される予定です。
カスタマーハラスメント対策の強化
法改正の中心となるのが、カスハラ対策の義務化です。
具体的には、以下のような措置が求められています。
・カスハラに関する相談体制の整備
・研修やマニュアルによる社員教育の実施
・実際にカスハラに遭った際の対応体制の整備
・加害者(顧客)に対する注意喚起や対応拒否などの判断指針の策定
従来は顧客優先の意識が社会で高かったこともあり、そのことで従業員のケアは後回しともいえる風潮でしたので、会社の対応策はどうしても消極的な対応にならざるを得ませんでした。
今後は、法的根拠をもとに会社はクレーム等に対する考え方の社内の基準を定め、体制を整備することで従業員を守ることにつながり、働きやすい環境の整備が可能になります。
顧客満足度を保ちつつ、従業員の尊厳と健康を守る、バランスの取れた対策が求められるでしょう。
企業ができる現実的なカスハラ対策

法改正によってカスハラ対策が義務となるなかで、無理なく、現場で運用できる体勢を整える必要があります。
以下では、規模や業種を問わず導入しやすい5つの現実的なカスハラ対策をご紹介します。
- カスハラの明確な定義と社内通知
まずは「どのような言動をカスハラと捉えるか」を社内で明確にし、従業員全体に共有することが大切です。
例えば「業務と関係のない私的な要求」「暴言や人格否定」「土下座の強要」など、具体例を挙げることで、従業員自身が「これはカスタマーハラスメントだ」と認識しやすくなります。
また、社内掲示板や就業規則への反映を行い、企業としての姿勢を示しましょう。
- クレーム対応の「限度」を明文化する
サービス業や小売業では、クレーム対応の線引きが曖昧になりがちです。
そこで、対応可能な範囲・お断りする基準をマニュアルに記載し「一線を越えた場合は対応を打ち切る」旨を明文化しましょう。
顧客対応マニュアルの見直しに加え、実際に、店舗やWebサイトに「以下に該当するような行為をカスタマーハラスメントとし、適切に対処いたします。」といった文言を掲示する企業も出てきています。
- 相談窓口の設置と「言いやすい」空気づくり
カスハラ被害があっても、上司に伝えることをためらってしまう従業員は少なくありません。
そのため、外部に相談できる窓口の導入(社労士や産業医など)や、直属の上司以外に相談できる体制の整備が重要です。
「こんなことで相談していいのか?」と迷わせないよう、日頃から言いやすい空気づくりも現場には不可欠です。
- 定期的なロールプレイング研修
カスハラは突発的に起こるため、マニュアルだけでは対応が難しい場面も多いです。
そこで、実際の事例をもとにした研修を行い、現場社員の「いざというときの対応力」を養いましょう。
研修は、現場社員を中心に行い、直属の上司や管理職の社員も巻き込み、対応後の報告体制やフォローについても習得してもらいましょう。
- 被害後のケア体制を整備する
カスハラに遭った従業員が「自分が悪かったのかも」と、自己否定に陥ってしまうことも珍しくありません。
カスハラ被害が起きた際には、迅速にメンタルケアや配置転換などを検討することが大切です。
場合によっては産業医や社労士など外部の専門家と連携し、長期的なケア体制を構築しましょう。
従業員を守り、安心して働き続けられる職場を実現するためにも、まずはできることから対策を進めていきましょう。
カスハラ対策を怠った場合の罰則やリスクはある?

法改正によってカスハラ対策が義務化されるとはいえ、違反した場合にすぐに法的な罰則があるわけではありません。
しかし、対策を講じない状態は、行政指導の対象になる可能性や、企業の社会的信頼を損なうリスクがあります。
代表的なリスクについてみていきましょう。
罰則は無いが行政機関からの指導を受ける可能性がある
しかし、ハラスメント防止措置の不備が認められた場合には、行政機関から「助言・指導・勧告」を受ける恐れがあります。
社内ルールや相談窓口、研修の実施状況などの対策ができていない場合には、改善を求められるリスクは高いでしょう。
口コミやSNSでの評判から炎上するリスクがある
カスハラ被害に対して企業が何の対応も取らなかった場合には、企業の信頼を損なうリスクがあります。
「ブラック企業」「カスハラ放置」といった投稿がSNS上で流れ、炎上するような事態になったことで、企業イメージの低下や採用活動への影響、顧客離れのリスクがあります。
もはや、カスハラ対策は企業にとって必須と言えます。
問題を放置すると優秀な人材が離職する可能性も
カスハラが常態化した職場では、従業員のモチベーションの低下、精神疾患の罹患率が高いと言われています。
この状態を放置してしまうと、「優秀な人材から辞めていく」「離職率が高くなり、人材育成ができない」といった問題を抱える、いわば「余裕のない職場」になり、競争力のある強い会社からほど遠い状況に発展しかねません。
人手不足が深刻化する現代においては、従業員が安心して長く働き続けられるよう、カスハラ対策が不可欠です。
まとめ
2026年から施行予定の労働施策総合推進法の改正により、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が企業の義務になる予定です。
企業は従業員の心身の健康・安全の確保に努めつつ、安心して働くことができる、本来の業務に専念できる、職場環境の整備をしていく必要があります。
カスハラが起きにくい環境になるようマニュアルを整備する、カスハラが起きてしまったときには迅速・適切に対応することで、従業員を守る会社の姿勢を示すことになり、会社の健全な発展につながっていくでしょう。