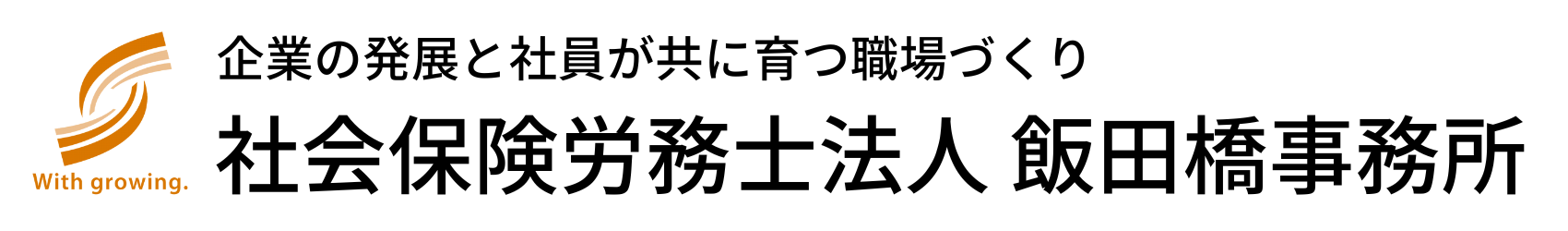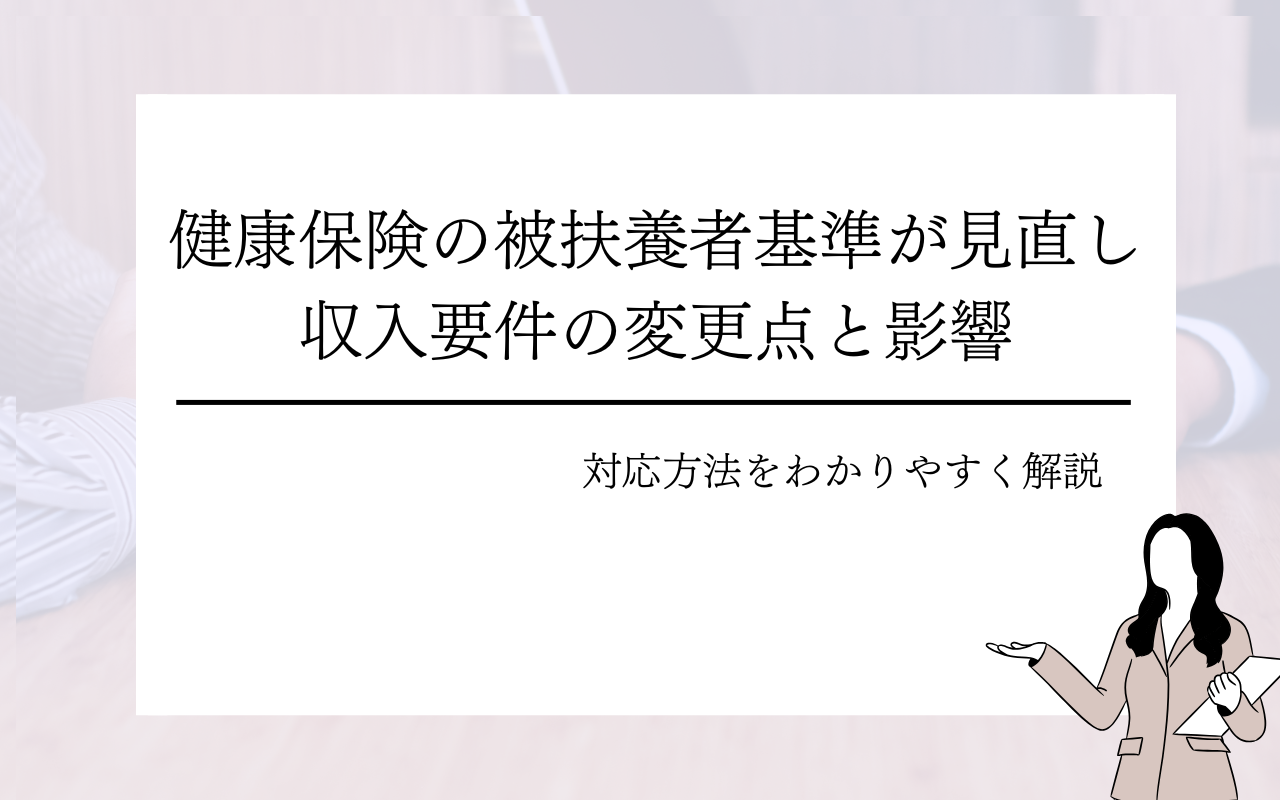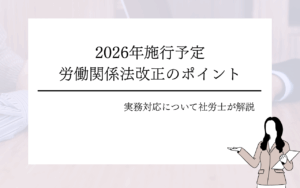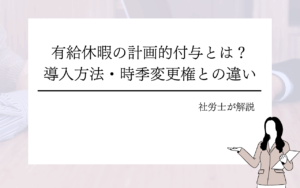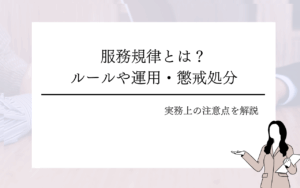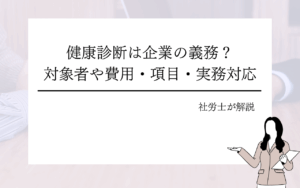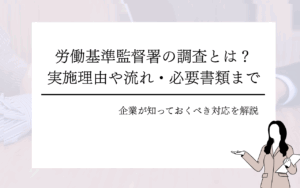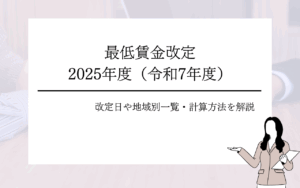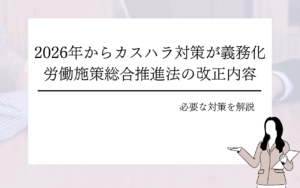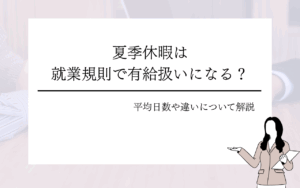2025年5月、厚生労働省が健康保険の被扶養者基準に関する重要な見直しを公表しました。
見直しにより、2025年度(令和7年)10月から、19歳以上23歳未満の被扶養者の年収要件が「150万円未満」へ引き上げられます。
これまでの「130万円未満」という基準からの変更となり、その影響は被保険者やその家族だけでなく、企業の人事・労務担当者にも現れてくるでしょう。
本記事では、被扶養者基準の見直し内容から背景や企業側で求められる対応まで、社労士の視点から解説します。
人事・総務担当者や学生を扶養している世帯主の方は、ぜひ最後までご覧ください。
令和7年10月から年収要件が150万円未満に【19歳以上23歳未満対象】

今回の見直しにより、健康保険の被扶養者における「年収の要件」が一部の年齢層に限って緩和されます。
具体的には、19歳以上23歳未満の若年層(学生・非学生問わず)で、これまでの「130万円未満」から「150万円未満」へと引き上げられます。
年間収入の見積額が150万円未満であれば、健康保険の被扶養者として認定され、実施は【令和7年(2025年)10月1日】からです。
アルバイトやインターンシップなどの収入において、「130万円の壁」によって扶養から外れるリスクが軽減されるため、被扶養者・扶養者の双方にとって大きなメリットとなるでしょう。
そのため、企業としては年齢や収入見込みなどの確認を丁寧に行う必要が出てくるでしょう。
なぜ見直し?健康保険の被扶養者基準が変わる背景

健康保険における被扶養者の収入要件が見直される背景には、社会構造の変化と制度の歪みへの対応が挙げられます。
特に注目すべきは、いわゆる「130万円の壁」問題と、少子高齢化に起因する労働市場の変化です。
「130万円の壁」問題解消
これまで、被扶養者として健康保険に加入するための年収基準は「年収130万円未満」とされてきました。
この基準を超えてしまうと、自分で健康保険に加入する義務が生じ、保険料も自分で負担しなければなりません。
そのため、特に学生や専業主婦は、年収が130万円を超えないように勤務時間を調整する「就労抑制」を行っており、労働力が活用しきれていない状況がありました。
今回の見直しでは、該当する若年層に限って年収基準が緩和されることで、部分的な「130万円の壁」問題の解消が期待されています。
少子高齢化に伴う労働力不足への対応
「130万円の壁」問題以外にも、日本全体の少子高齢化進行により、企業では慢性的な人手不足が課題となっています。
特に現役世代として働ける若年層の労働力は、経済活動を維持するうえで欠かせない存在です。
厚生労働省が今回の見直しに踏み切ったのも、学生を含む若年層の就業を促進し、全体の労働力の底上げを図る狙いもあるでしょう。
現行の健康保険における被扶養者の認定基準とは?

健康保険制度において、被扶養者として認定されるためには、収入や生活状況に関する一定の要件を満たす必要があります。
変更点を的確に押さえるために、現行の健康保険制度における認定基準を改めて確認しておきましょう。
被扶養者となる人の範囲
被扶養者とは、健康保険に加入している「被保険者(たとえば会社員本人)」によって生計を維持されている家族のことを指します。
具体的には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など、三親等以内の親族が対象です。
同居・別居の有無や生活の依存関係によって、認定されるかどうかは変わってきます。
たとえば、別居していても仕送りなどで生計を維持している状態であれば、被扶養者として認定されるケースもあります。
年収要件
収入面の基準は、被扶養者の認定可否を左右する重要なポイントです。
現行制度では以下の2点で判断しています。
・年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であること
・被保険者の収入の2分の1未満であること
さらに、同居しているか否かで判断基準も変わります。
なお、年収の判断は「今後1年間の見込み収入」を基準としており、一時的に収入が増えた場合でも、安定的な収入とみなされない限り、扶養から外れることはありません。
ただし、就職やアルバイト開始など、恒常的な収入増加が見込まれる場合には、企業が収入証明や雇用契約書などをもとに判断する必要があります。
年収要件の見直しによる影響
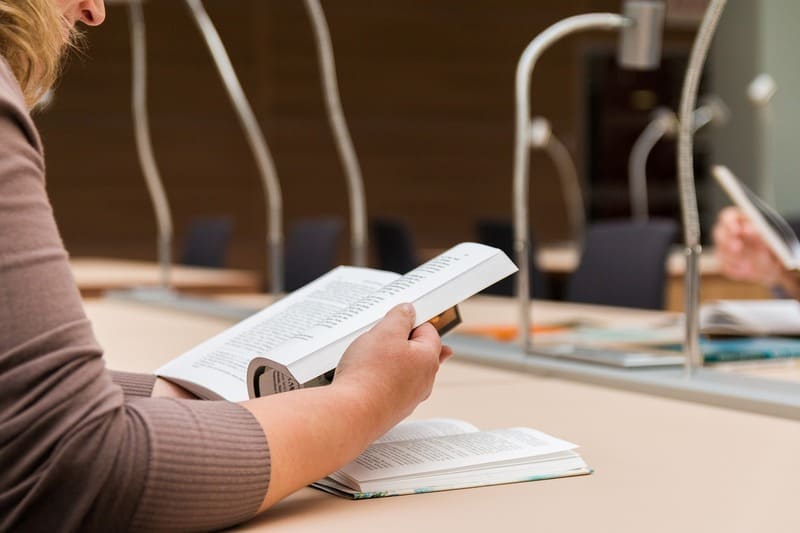
今回の見直しにより、被扶養者の年収要件が「150万円未満」に緩和されることで、被保険者・被扶養者・企業それぞれに異なる影響が生じます。
特に企業側では、実務上の注意点を早めに把握しておく必要があるでしょう。
まず、対象となる19歳以上23歳未満の若年層については、これまで年収130万円を超えた時点で被扶養者から除外されていたところが、年収150万円までであれば継続して扶養認定が可能となります。
これにより、学費や生活費のために働く若年層の就労制限がやや緩和されることになります。
一方で、企業の人事担当者の業務はこれまで以上に複雑化する可能性が高いです。
対象年齢の確認から年収見込み額の正確な試算、証明書類の提出依頼など、個別の判断業務が増加することが予想されます。
また、見直しの対象外となる被扶養者については、従来どおり130万円未満の基準が適用されるため、「年齢によって基準が異なる」という複雑さに注意が必要になるでしょう。
さらに、企業によっては扶養人数の増加に伴う保険料負担の増加や、制度変更を適切に周知する体制が求められるでしょう。
企業や人事担当者がすべき対応とは?

被扶養者年収基準の見直しにともない、企業の人事・総務部門では、制度変更を適切に業務へ落とし込む対応が求められます。
ここでは、実務的に行うべき具体的な対応を3つ解説します。
要件変更の内容を社内・従業員に周知する
まず最初に行うべきは、制度改正の内容をわかりやすく社内に通知・共有することです。
特に、対象となる19歳以上23歳未満の扶養家族がいる従業員に向けて、変更の趣旨や収入要件の新基準(150万円未満)を明確に伝える必要があります。
扶養家族がいる従業員への通知文やFAQの作成、社内掲示板への掲示など、情報伝達手段を複数用意しておくと誤認防止につながるでしょう。
収入見積もりや扶養可否判断を新基準で行う
令和7年10月以降の申請については、対象年齢の被扶養者に限って「年収150万円未満」での判断が必要となります。
「対象年齢に該当しているか」「収入が150万円未満か」を慎重に確認し、被保険者から提出される収入証明書や雇用契約書などの書類を確認しなければなりません。
変更による懸念点の共有・相談
制度改正に伴って、疑問や不安を抱える従業員が増えることが想定されます。
たとえば「今年の収入が140万円だけど、来年はどうなるのか」「アルバイトの時間が増えて基準を超えそうだがどうすればよいか」といった相談が寄せられる可能性があります。
こうした個別対応の負担を軽減するためには、社会保険労務士との連携や、問い合わせ窓口の整備、従業員向けのQ&Aを用意することがおすすめです。
特にパート・アルバイト層が多い企業や、学生アルバイトを受け入れている企業では、周知・相談体制の整備が大きなポイントとなるでしょう。
まとめ
令和7年10月から実施される健康保険の被扶養者基準見直しにより、19歳以上23歳未満の被扶養者に関して、年収要件が「130万円未満」から「150万円未満」へと緩和されます。
この変更により、若年層の働き方の自由度は高まりますが、企業や人事担当者は新たな判断基準をもとに対応する必要が出てきます。
今後は対象年齢の確認や収入見込みの判断、社内通知の強化、相談体制の整備が重要になるでしょう。